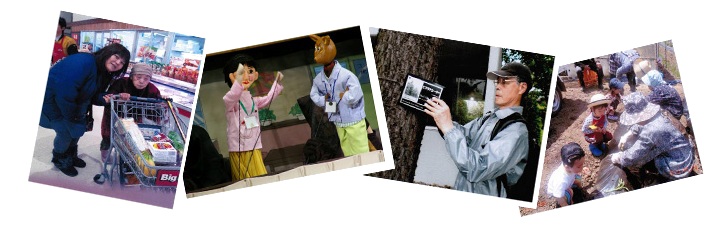水沢南大鐘寿会


水沢南大鐘寿会 会長 高橋 安三郎 会員数 63名 設立年月 平成16年月
所在地 〒023-0855
奥州市水沢南大鐘1-7
電話 0197-24-5069
連絡先〒023-0855
奥州市水沢南大鐘109-4
電話 0197-24-4736(携帯090-9534-9460)6名
助成事業について
1.いきいき人生「演芸みなみ寿座」の設立
高齢社会を迎え、元気高齢者の地域社会参加が大切な時代となった。平成26年、寿会設立10周年を記念し、高齢者の豊富な知識・貴重な経験、また長年培った趣味などを生かして地域社会奉仕活動参加の一環とし「いきいき岩手支援財団」の助成をうけて「演芸みなみ寿座/高橋安三郎座長」を設立した。
【踊り・マジック・フラメンコ・歌謡・スコップ三味線・民話、協力ゲスト等も参加し、それぞれの特技を活かし、「費用は自弁、報酬は感動」をモットーにボランティア奉仕活動】
(1)震災復興支援、被災地仮設住宅慰問公演
震災から3年を経た平成26年3月、被災地の皆さんに「演芸」を通じて仮設住宅皆さんに、笑顔と元気を届けようと、被災地訪問活動をスタート。お寺さん(興性寺・江刺、龍徳寺・水沢)や薬王院(東京八王子)からの参加で、災害犠牲者の慰霊供養、お楽しみ演芸、そして仮設住宅参加の皆さんとテーブルを囲み「暮らしの事、悩み、被災地の今」などを語り合う「お茶っこ懇談」を行った。そして、被災地の現状・課題・被災者皆さんの暮らしなどを会議や情報発信などで紹介し被災地支援の輪が少しでも広がるようにと努めた。 平成26年から5年間にわたり、大船渡市,陸前高田市等の仮設住宅、災害公営住宅等、延べ12回・23カ所の訪問公演となった。
(2)「見て、聴いて、ふれる/三鉄列車で行く被災地交流の旅
震災から7年となった平成29年7月8日、いきいき岩手支援財団の助成により、三陸鉄道南リアス線の復旧支援を兼ねて「見て、聴いて、ふれる列車で行く被災地ふれあいの旅/大船渡盛駅~釜石駅」を企画実施した。列車内で現地ガイドによる沿線の「あの時~そして今」の震災講話や大船渡市街地視察、そして大船渡地の森仮設住宅皆さんとの交流懇談など、被災地の現状の多くを学んだ。
(3)日創協季刊誌「まち・むら」誌上通じて全国に広く紹介
三鉄列車で行く被災地交流の旅に、かねて情報交流を重ねている「あしたの日本を創る協会/・東京」から記者・カメラマンの同行取材があり、被災地の現状や仮設に暮らす皆さんが抱えている生活課題などが全国まちづくり情報誌「まち・むら139号」で、全国各県・市町村や関係団体等に配布され紹介された。(2017年9月発行/カラー5ページ)
2.「忘れない、風化させない3.11」/元気・笑顔・ふるさと交流讃歌
平成30年7月11日、被災地大船渡市内仮設住宅・災害公営住宅の皆さんを奥州市に招待し、心の復興を願いふる里流を実施した。
震災発生から8年(月命日)、被災地の復興は未だ道半ばにあり、街や道路などハード面の復興はすすんではいるが、被災地皆さんの心の痛手は時間が経っても癒えることはない。災害公営住宅や戸建て住宅建設で仮設からの転出移住が進む中で事情等により仮説住宅に留まざるを得ない人達もいる。
こうした現状をふまえて、「元気・笑顔・ふるさと交流讃歌」を企画し、演芸ステージを農村風景の濃い奥州市胆沢に交流特設会場を設けて、演芸を楽しみながら、被災地の状況を語り合う、ふる里交流懇談や震災犠牲者の慰霊供養、被災地支援事業所訪問を実施した。
令和元年7月9日(予定)に、奥州市に移住されている被災者皆さんと陸前高田市災害公営住宅のみなさんを招待し、「被災地の想い、心のふれあい・ふるさと交流会」を開催し、震災犠牲者の慰霊供養(協賛寺院)、震災復興支援事業所見学、そしてお楽しみ演芸ステージで心を癒し、ふるさと談議等で「忘れない、風化させない3.11」を心に刻み、演芸を通じて復興支援を継続推進する。
3.福祉施設、各祭事等への出前公演活動
福祉施設やディサービス、ケアハウス、特養老人ホーム、敬老会、祭り、高齢者サロン等、市内各地域の催事等にボランティア出前公演を実施。
震災復興支援・被災地仮設住宅慰問活動等がマスコミ紹介により、地域の出前公演にも広がった。この中で「いきいき岩 手支援財団事業」や被災地の現状等を紹介し、少しでも被災地への想い、支援の輪が広がることに努めている。(市内各施 設、催事等26回)
4.三世代間交流とふる里歴史の山河探訪講話【平成30年11月18日/水沢南地区センター】
子供会・子供会育成会(保護者)・高齢者団体による世代間交流会において、ふるさとの歴史探訪で見て・聴いて、現地に学んだ「誇れるふる里の歴史」を、史跡図面を貼示しながら義経夫妻の位牌安置の経過、安倍氏と平泉藤原氏、一首坂の歌 合戦の話など丁寧な解説を加えて語り伝えに笑顔と拍手が広がった。子供たちも目を輝かせて聞き入り、保護者の育成会か らも「勉強になった」と感謝の声が寄せられた。講話後のグループ交流でもふるさとの歴史が話題になるなど、次世代伝承 事業としての成果を見ることができた。


助成事業以外の活動について
- 三世代間ルンルンなかよし交流会
高齢者・子供会・子供会育成会(保護者)による世代を超えての交流、子供たちを主役に大人はサポーターとして「ふる里懇談、スポーツ、ゲーム交流」等。 - 野外散策ふる里歴史探訪
元気・健康づくりをかねて地域の歴史を学ぶ - 環境美化花いっぱい運動
町内市道交差点「導流島花壇・5コーナー」に約1,200本の花の植栽・除草・水かけ作業など通年的に実 - 会報「瓦版 ことぶき」の発行
毎月発行(A4版)、会員及び関係団体等に情報交流紙として配布 - その他、新春あいさつ交賀会、一泊旅行、芋の子交流会、シニアスポーツ大会参加、他



結成までの経緯
- 平成23年3月11日、東日本大震災が発生した。大槌町の被災家族が親戚のお世話で町内に避難生活に入り、町内ぐるみで日用品、暖房器具、生活用品など持ち寄って生活支援をおこなったことを契機に被災地への激励・慰問活動が話題になり、芸達者な仲間による「演芸」の立ち上げにつながった。
- 演芸公演に関わる関係資材(太鼓・のぼり・半纏・拍子木・他)は、いきいき岩手支援財団の助成で準備ができ、またゲスト出演協力も増え、踊り、フラダンス・マジック・歌謡・ギター・スコップ三味線・民話等、レパートリーも広がり楽しい演芸ステージを届けることができた。
- 被災地仮設住宅訪問公演は、着替えの場所もないことから、踊りの着物衣装(自宅で着用)での参加、マジック資材の搬入等 のためバスの準備が悩みとなった。被災地まで長距離(約70K)等もでもありかだいとなったが、地域の自動車学校の協力も いただき、感謝の訪問公演ができた。
- 震災復古支援公演がマスコミ等で紹介されたことにより、*被災地仮設訪問で演芸後のお茶っこ懇談をもって、厳しい生活の現状や悩みなど伺い、情報や集会で紹介している。
活動回数
助成事業「演芸みなみ寿座」の活動
(1) 震災3.11「心の復興支援」として、年2回の企画 福祉施設、地域催事ボランティア出前公演 年5~10回(予定)
事業効果は?
- 「演芸みなみ寿座」結成により、被災地仮設住宅訪問に足を運び、被災者皆さんとの懇談の中で暮らしの実態や悩みなど多くを学ぶことができた。
- 短い公演時間でも仮設住宅皆さんの心の悩みや孤独感を癒し、笑顔と元気交流ができた。
- 被災地、被災団体等の交流に大船渡市ボランティア団体「夢ネット大船渡/岩城恭治理事長」との連携ができた。
復興支援にかかわる情報提供やイベント企画等に協力いただき、また仮設住宅訪問や被災地みなさんを内陸に迎えての「被 災者招待ふるさと交流」の開催ができた。、
- 福祉関係施設等に出前公演を行う機会に「被災地の現状」を伝え、少しでも被災者に心を寄せ支援の輪が広がることにつながった。
今後の予防など
- 震災3.11から9年となる。今なお行方不明者1,000余名を数える。仮設住宅も公営災害住宅や戸建住宅へと転出がすすんでいるが、県内の仮設住宅は875世帯(1,880人/4月末現)の現状にある。
仮設住宅自治会も解散となり、残された仮設住民みなさんの暮らしは新たな課題を抱えている。これからも被災地ボランティア団体「夢ネット大船渡」との連携をはかりながら、震災復興支援「演芸みなみ寿座」ボランティア公演を通じて、被災地皆さんの心の復興にお手伝いできるように継続交流をはかりたい。 - 福祉施設、ディサービスやケアハウス、地域催事等にも仲間の都合等配慮し、ボランティア出前公演を継続していくことが大切と感じている。
団体のPR
- 「今日を楽しく、明日に夢を」をモットーに、隔月に理事会を開いて自由放談、その中でいろんなアイディアが生まれる。
- 事業の実施は、「担当・世話人会」を設けて企画し、全員の協力で運営する。
- 一人暮らし、ひきこもりがちな高齢者の皆さんにも声をかけて高齢者サロンや各種事業等に誘いあって参加をはかっている。
- 情報を共有しながら、各種団体との交流を大事に、元気高齢者の輪を広げている。
- 後藤新平伯の自治三訣「人のお世話にならぬよう人のお世話をするよう、そして報いをもとめぬよう」を心に、「費用は自弁、報酬は感動、心の豊かさ完全支給」をモットーに、高齢者の元気・笑顔が広がる活動をつづけている。