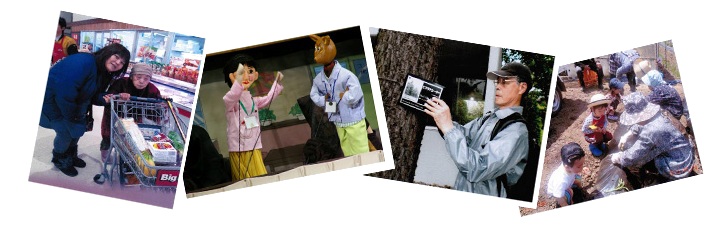宮澤賢治「下の畑」保存会
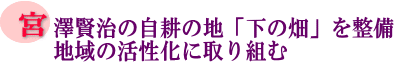
宮澤賢治「下の畑」保存会
平成20年、花巻市で結成 会員数6名
会長 菅野 将勝
連絡先 0198-24-5672(松田 廣邦)

助成事業について
- 宮澤賢治の自耕の地「下の畑」を耕作し年間を通じて時季の野菜を植栽し、良好な状態を維持することがでできた。
- 花壇「涙ぐむ目」への花苗の植菜を行った。花壇枠をブロックで整備し、従来に増して花壇としての良い体裁が整った。
- 地域の高齢者等の協力が得られ、花壇への花苗の植栽や水やりの際の大きな人力となった。
- 賢治に関した事柄を、花苗・野菜苗を植え付けた時に、老人クラブ、学校、地区PTAとともに、講師から説明を受けた。
- 全国からの観光客への説明や案内について、会員の知識向上を図るため講師を招き「賢治に親しむ勉強会」を2回開催した。
- 「下の畑」周辺小道の好環境化で「菜の花ロードへの種まき」「一本櫻と岩手山の眺望設定」に取り組んだ。
- 畑周辺の見晴らし環境向上のため、定期的に堤防沿いや畑回りの草刈りを実施した(定期6回および状況に応じて随時実施)。
助成事業以外の活動
会員は地区の老人クラブにも所属しており、地区の公園や賢治詩碑にいたる歩道の清掃やグランドゴルフ等の健康づくり、地域コミュニティ協議会の行事への参加も含め会員の親睦・交流活動を行っています。
結成までの経緯
宮澤賢治詩碑(雨ニモマケズ)から北上川方面へ約300メートルほどの川沿にある「下の畑」は、賢治が取り組んだ農民との交流の時代を象徴している場所です。
この貴重な場所を荒らしたままにしてはならないとの考え、地道な保存活動に取り組んできたものです。
従前は、この周辺は大変荒れていて、土手なども藪だらけで北上川が見えない状況でしたし、畑にしても雑草が生い茂り野菜作りもままらない状態でした。
そうした状況を見かねた現在の会長が、ブルドーザー等を地域から借り受け整地し、一定の区画を計測し、中央には賢治が設計した「涙ぐむ目 花壇」を模し、一つの枠組みを造り上げました。
並行して、この地を保存活用していくための協力者を求めたところ、賛同者が数人集まり、保存会として発足することができました。
資金も労力も会長による奉仕から始まった活動であり、信念と行動力がなければなかなか軌道に乗せることは困難であったろうと思います。


事業効果は?
- 会員同士が議論をしながら土壌改善、野菜の育成・収穫を行うため、良い結果がでています。
- ブロックの購入により花壇が整備され、より体裁の良いものに整いました。
- 地域の高齢者の理解と協力は、自らの生きがいづくりとともに畑の保全に大きな効果をもたらしています。
- 現地「下の畑」で行う講演や説明は、参集した各世代に実感を伴って親しみを感じさせています。
- ポイント設定や菜の花等の風景は訪れる人を心地よくさせる効果があります。
- 地元のみならず、全国から訪れる多くの観光客から、好感をもって受け入れられています。
活動回数
毎年3月下旬から12月中旬まで、年間を通じて活動してます。
農作業は通年、草刈りは定例6回および随時
勉強会(2回)
その他コミュニケーション等
今後の予定など
全国的に愛されている宮澤賢治。その自耕の地「下の畑」を訪れる観光客は、年々増えてきています。
保存会では、できるだけ周辺を整備し、訪れる方々に風趣を感じていただきたいと思っています。
中央の花壇についても、助成事業の承認により一定の形ができました。
この事業を継続することで、史跡としての環境が保たれ、地域での理解の輪が広がり、自然を大切にする心が育まれるよう期待しています。


団体のPR
保存会員は6名ですが、多くの賛助会員が大きな力となっています。
区長・町内会長・地区老人クラブ・PTA・振興センター、そしてコミュニティ協議会など、各方面への働きかけにより認知度も高まっています。
春の花苗の植栽、秋の野菜の収穫、特に「白菜」は、賢治との結びつきを求める人が、わざわざ仙台から白菜の苗を移送し、栽培しました。そして収穫して、各方面に提供しています。
当地「下の畑」の大きな課題は、大雨が降るとしばしば水浸する場所になってしまうことでしょうか。
毎年その復旧に労力を費やしながらも、秋の収穫を夢見て手をかけ、野菜の育成に取り組んでいます。
保存会員はまさに、「雨ニモマケズ」で頑張っています。