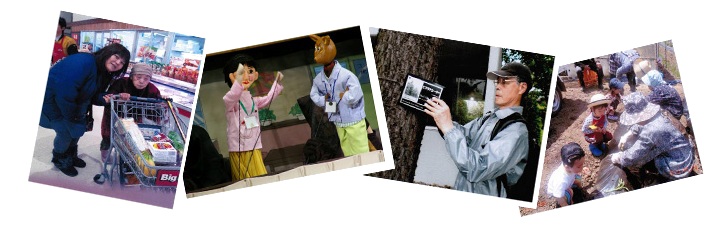高松第三行政区ふるさと地域協議会
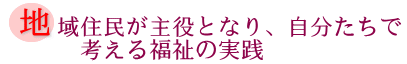
高松第三行政区ふるさと地域協議会
平成20年、花巻市で結成。会員数68名。
会長 神山 儀悦
連絡先 090-4638-9764
(事務局 熊谷 哲周)

活動内容について
助成事業
- 『高松第三行政区ふるさと交流福祉計画』策定にともなう講演会、ワークショップ、全住民アンケートの実施、印刷製本および全世帯への配布
- 『高松安心サロン』の試行実施
- 『未来に架ける世代間交流会』の試行実施
- 『困ったときの連絡先一覧』の作成および全世帯への配布
助成事業以外の活動
- 福祉センターとの連携による『共同農園』の設置
(デイサービス利用者に軽作業を提供し、健康づくりを応援。収穫した野菜を食材として提供)
- 交流による定住促進の取り組み
『名勝のライトアップ』や『花火大会』『地域案内人養成講座』等の実施
地元の先生が野菜づくりを教える貸農園『ふるさと農園』の運営
- 沿岸被災地(山田町船越地区)への野菜供給等の支援活動
助成事業を始めたきっかけは?
住民同士で地域の将来を話し合う中、「過疎化、高齢化、一人暮らし世帯・高齢者世帯の増加等の課題を解決していかなkれば地域の未来はない」という意見が一致し、平成20年に『地域の活性化』を目的に、全戸参加で設立した。
団体結成のために必要だと気付いた点は?
- 危機感の共有
漠然と考えていた地域課題を具体的に共有する機会の設定
(当協議では、住宅地図を拡大コピーして一人暮らし世帯や高齢者世帯をマーキングした。その結果、問題を具体的に把握できた)
- 危機感を形に
新たな組織の立ち上げによる課題解決
既存組織を活用して課題解決を図ろうとすると、事業負担増により進まなくなる恐れがある。目的を絞った新たな組織を立ち上げた方が活動しやすいこともある。
- 地域課題解決のビジョン
地域住民の目指す方向を定める。当協議会は、設立4年目にしてようやく「将来のあるべき姿」=「高松第三行政区ふるさと交流福祉計画」を策定することができた。

苦労した点
- 設立当初、組織はできたものの資金も何もなかったが、農水省の補助金を導入することができて解決した。
- 活動当初はノウハウも何もないために試行錯誤の繰り返しだった。その中で農水省(東北農政局)、花巻市(農政課)のアドバイスに助けられた。
- 活動を続ける中で地域住民から厳しい意見が出された。
「ソフト事業をすることで何かメリットはあるのか」
「もし失敗したら補助金は返還しなければならないのか」など
しかし、郷土芸能の「神楽」の伝承と後継者育成の活動の中で、地域の若者に声をかけたところ、今まで集会に参加したことがなかった20~30代の若者が10人参加し、活動の一環として神楽用の「太鼓」と「手びら金」を購入したことをきっかけに活動への理解は深まった。
事業効果や気づいたことは?
事業実施後の地域の変化
講演会、ワークショップ、アンケートの実施により、地域住民が「自分たちで考える福祉」という意識が芽生え、各種会合などでの話題になっている。
また、近隣行政区(集落)から活動内容の問い合わせがきている。
サロンの試行実施により、周囲から「自分たちでもできそうだ」という声が出ている。
『困ったときの連絡先一覧』を配布したことにより、全世帯で電話のある場所に貼っている。「個人情報保護法の関係で、近所の電話番号も分からなくなっていたので、本当に助かる」という声があがっている。
参加者の感想
ワークショップの参加者から、「生まれて初めてワークショップを経験したが、出された意見が実現できたら老後の心配がひとつなくなった」という感想が寄せられた。
今後の予定、課題
福祉の拠点となる「地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護施設)」の整備
一人暮らし世帯や高齢者世帯の「安否確認・緊急通報システム」の構築
お年寄りから子供まで気軽に立ち寄れる「コミュニティレストラン」の設置
地域の資源と人材を活かした「産業福祉(スモールビジネス)」の構築
地域の資源と人材を活かした「6次産業化」の取り組み
団体のPR
設立当初の「みなが主役、みんなで実践」をモットーとして活動を続けていきたい。