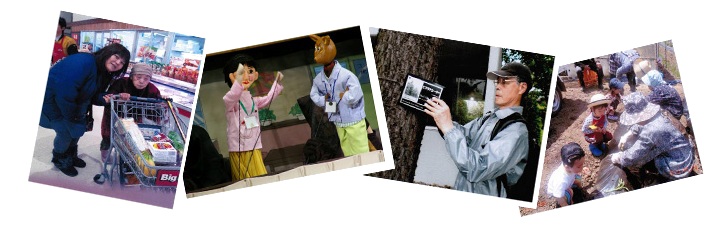地域おこし歴史懇話会
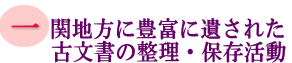
地域おこし歴史懇話会
平成20年、盛岡市で結成 会員数17名
会長 鈴木 幸彦

助成事業について
- 近世村方史料の整理・保存
- 一関市内に現存する古文書の整理、保存(市民センターなどを使用し、ボランティアとともに作業を行い、整理したものは目録を作成する)
- 古文書入門講座
- 古文書に興味がある一般の人を対象に古文書の講座を開催
- その他、専門の有識者を招き講演会や座談会を開催
結成までの経緯
一関地方に豊富に遺されている近世村方史料(いわゆる古文書)をもとにした、客観的・合理的な地域史の掘り起こしによって、地元に定着した息の長い地域おこし事業に寄与する目的で、地域の歴史に関心を持つ高齢者を中心に平成20年に設立。
専門研究者による最新の研究成果を学ぶ歴史講演会、地域住民や高校生のボランティアによる古文書の整理・保存事業などを開催している。

活動回数
- 年4回
今後の予定など
- 地域の住民が講師となって各種古文書講座(できれば藩政時代の旧村単位で)や、小学生を対象とした親子古文書教室などを開催して、古文書への関心を広め、さらに古文書の調査・整理・保存活動に携われる方向を確立したい

事業効果は?
- もともと学術的内容を有する文化活動は、一般市民に広がらない傾向があるが、当会の事業に協力いただいた人たちには一定の評価がある。とくに小学生や高校生は、初めて生の史料に触れる感激と、一つでも二つでも字が読めるようになったという喜びと、少し賢くなったという喜びは、学ぶ喜びの本質を示すことと思われる。
そのうえ、高齢者にとっては、若い人との共同作業に、大きな喜びと楽しさを感じ、若返りには最適と思われ、両者ともこのような機会があれば、また参加したいと述べている。
ただし、高齢化による会員の減少と事務局体制の脆弱さ、壮年層への対応策が課題である。
団体のPR
もともと古文書は、2000年前からの中国の漢字文化圏において、神に墨書する記録方法が始まりで、それが日本に伝わり、特に近世日本において、将軍から町や村の庶民たちに至るまでに広まり、日々大量に文書が作成されるようになったものである。
この文書は、盛岡藩においては、全国に誇れるほどの大量の藩庁文書が遺されており、仙台藩・一関藩においては、村方文書が、全国的にも例がないほど大量に遺されている。
これらの文書は、貴重な文化財として後世に永く伝えられるべき文化遺産であり、解読し研究することが重要であると考える。