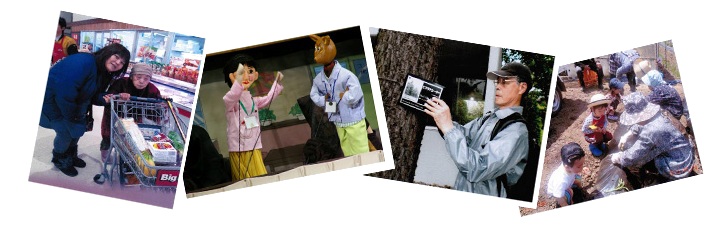ボランティアグループ「もやいの会」
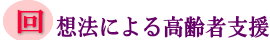
ボランティアグループ「もやいの会」
平成21年、宮古市で結成。会員数21名。
会長 佐々木 美佐穂
連絡先 090-9754-2204(本山 潤一郎)

助成事業について
- アクティビティプログラム実践
- 過去にプログラム実践した仮設住宅の高齢者を対象とした同窓会の実施
内容 宮古第二中学校仮設住宅に入居する高齢者を対象とした人形劇や歌唱などのレクリエーションプログラム - 仮設住宅の高齢者を対象としたグループ回想法の実施
内容 宮古水産高校第2グランド仮設住宅に入居する高齢者を対象としたグループ回想法プログラム - 市内在住の高齢者グループ回想法の実施(宮古市内仮設住宅に入居する高齢者を含む)
- 過去にプログラム実践した仮設住宅の高齢者を対象とした同窓会の実施
- 事業運営会議
会員による年間の実施事業の振り返りと、次年度の事業に向けた協議
(グループ回想法とは)
過去の出来事や体験を思い出し(回想し)、それについて話し合う心理療法。同会では、宮古市内の仮設住宅に入居している高齢者や介護予防教室に参加する高齢者等を対象に、グループ回想法を行っています。5~8名程度の参加者と、進行役のリーダー、リーダーと協力するコ・リーダーで構成されます。話し合いのテーマ(例:「忘れらない味」「幼い頃褒められたこと」など)を決め、参加者はそれについて話し合い、お互いの思い出を共有します。回想法には様々な効果があると言われており、介護予防や認知症予防のプログラムとしても注目されています。
結成までの経緯
平成16年、国の介護予防モデル事業のプログラムの一部として実施されたグループ回想法。平成17年度からは、介護予防及び認知症事業の閉じこもり予防プログラムとして3か年計画で展開されました。平成19年度には、回想法を地域で継続的に実施できる環境を整えるため、ボランティア養成講座や、講座を修了したボランティアによるグループ回想法が実施され、もやい会結成につながっていきました。
平成21年度、継続的に回想法を実施するためには、組織をつくる必要性があるとの講座修了者の声から、ボランティアグループ「もやいの会」を立ち上げました。
結成時の会員は11名で、会の結成前より回想法の展開を支えていた宮古保健センターの協力も得ながら、地域のサロンや各種教室でのグループ回想法を年数回実施しました。
会の名称は、船をロープで係留する際のロープの結び方「もやい結び」から意を得ており、回想法を通して人々を繋ぎ止めることができればとの思いが込めらています。
東日本大震災発生後、会員間でボランティア活動について情報交換を行い、「(被災した住民からは)地域の人が来ると安心する」などの声が聞かれたため、活動を開始しました。
平成24年度、震災の影響による高齢者の閉じこもり、孤立、認知症の発症を予防するために、市内仮設住宅や地域介護予防や地域介護予防教室等で、グループ回想法や研修を開始しました。
併せて、継続的なプログラム実施には、経済的基盤が重要であると認識から、いきいき岩手支援財団への助成金申請を行いました。
現在も、高齢者の閉じこもり・自殺うつ予防に焦点を当て、活動を継続しいます。


事業効果や気づいたことは?
参加者からは「また回想法に参加したい」「次回また参加したい」などの声が聞かれており、グループ回想法の継続的な実施が、仮設住宅入居者等の閉じこもり・自殺・うつ予防に寄与していると考えています。
今後の予定、課題
- 地域介護予防教室でのグループ回想法
- 仮設住宅でのグループ回想法
- 仮設住宅を含む市内在住高齢者を対象としたグループ回想法
- 課題…継続的に活動するための予算確保手立て
- 取り組んでみたいこと…会員が移動するための交通費が確保できるなら、活動範囲を広げたいです。
団体のPR
東日本大震災後、地元のボランティア団体として、仮設住宅に住む方たちの閉じこもり予防のための活動を継続しています。
回想法は、参加する相手の方にとってだけでなく、実施する私たちにとって得るものが多いことが魅力です。
多くの人に参加してもらい、回想法について広く知っていただけるよう活動を続けています。