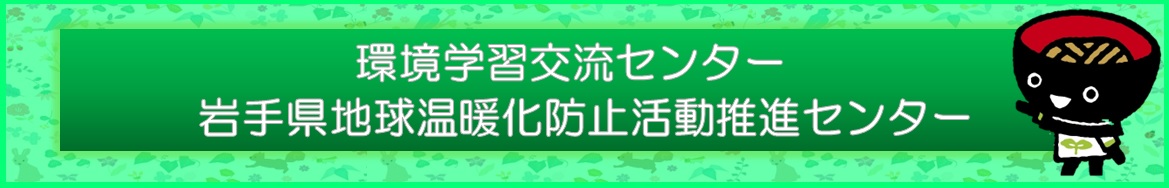岩手県内先進企業取材レポート
<第四回目> 一般社団法人ゴジョる
被災地発の林業×福祉×労働×環境をインクルージョンした事業を展開
誰もが住み続けたいまち「かまいし」を目指して ~一般社団法人ゴジョるの取組みについてご紹介~
東日本大震災津波から12年が経過した岩手県釜石市を拠点に、「サステナブルなまちづくり」を目指して活動を続ける(一社)ゴジョる釜石支店(以下略:ゴジョる)。
ゴジョるは、高齢者や未就業者といった福祉領域での支援対象者に向けて、地元産の未活用な木質資源を「薪」に加工して販売する仕事を創り出し、社会参加の場づくりを行っています。昨年度、この被災地発の林業×福祉×労働×環境をインクルージョンした事業が評価され、環境省が主催する「2022年度第10回グッドライフアワード」にて環境大臣賞地域コミュニティ部門を受賞しました。
今回は、ゴジョる代表理事の菊池隼(じゅん)さんに、立ち上げの経緯、事業と環境問題とのかかわり、活動のやりがい、今後についてお話を伺いました。


[一般社団法人ゴジョる 代表理事 菊池さん] [薪は、根浜シーサイドのキャンプ場でも販売している]
◎団体立ち上げの経緯について
東日本大震災後、被災者支援活動に従事していた菊池さん。年を追うごとにハード面での復興が進む一方で、被災者の方でもとくに高齢者や生活困窮者、若年性未就業者といった、一般的に社会的弱者といわれる人たちが、復興に向けての生活設計に大きな不安を感じていることをアンケート調査で知りました。
(菊池さん)「社会的弱者に対しての生活支援を福祉関係者の皆さんに相談するんですが、相談窓口では一般企業を紹介するしか選択肢がないんですよね。65歳以上の高齢者になると、人口減少や災害後などで地域経済が弱くなってきている所では、紹介できる仕事が数えるくらいしかなく、相対的にその仕事からもあふれた人たちがでてきてしまうんです。その方たちが安心して住み慣れた場所で最後まで暮らせる、それを支える仕事って何だろうと、色々な団体や企業にヒアリングを行いました。あるとき釜石地方森林組合の久保組合長(当時)から、家庭用の薪って需要が見込めるのだけど、片手間にやっていたらコストがかかり、ものすごく高い薪になってしまいなかなか流通できないし、薪を製造販売して店舗に卸して販売してるところって意外にないんだよね、という話を聞いたんです。おりしも震災からの生活再建で新規に住宅を立て直す方には、震災時にライフラインがすべて止まってしまった経験から、薪ストーブを導入する家が増えてきていることもあり、これは、ビジネスチャンスになるのではないかと考えました。弱者の方も一緒にみんなで『助け合いながら』薪を作って、販売するところまでやってみよう、と。」
かくして菊池さんは、2017年に5名で(一社)ゴジョるを立ち上げることとなり、事業をスタートしました。そして立ち上げから約7年経過した現在では、月80~90トンの大ロットで薪の生産・加工を行い、東北6県の日用品大手小売チェーンに納品するまでに団体の活動は大きく成長を遂げました。
(菊池さん)「現在は市内で50名近くの登録をいただき、毎日作業しています。作業に従事している方は男性が8割、女性が2割くらいの割合で、男性が多いです。以前被災者のコミュニティ形成支援活動などでお茶っこの会をやった時には、女性しか来なくて・・。男性はプライドがあって、自分の役割がないと動かないから、孤立しがちなんです。なのでこの作業場が、地域のコミュニティ形成の場にもなっているんです。」
◎事業と環境問題とのかかわり
順調に事業を拡大するにしたがい、製造する薪のロットも大きくなっていきます。スタート当初は森林組合から地元産の支障木や間伐材、製材等で発生する未利用廃材を調達していたものの、いよいよ木材が不足することに。そこで地元に小規模な山を持っている地主さんに木材提供の相談をしたところ、快く協力をいただけることになりました。
(菊池さん)「事業を立ち上げた当初は、正直、環境問題はそんなに考えていなかったんです。だけど山をもつ地主さんとお話をさせていただくと、木が全くほったらかしの状態となっていて実は困っていたと。ならばとその山にあった木を伐採し、薪作りに活用することになりました。私たちが整備することで、地主さんにも喜んでもらえて、土も元気になります。
又間伐したあとの土壌に、新しい木を植えることで木の CO2の吸収量も良くなるし、事業の持続可能性にもつながります。第一、木材を遠くから燃料をかけて調達するなんて、無駄にお金もかかるんでやりたくないですよね。結局、地元にお宝があったんですよ。効率的に事業を進めるためにはと考えていったら、地域資源をとことん活用することに気づいて、それが実は環境にも良い取り組みになっていたんです。それからは環境問題についても取り組んでいこうと思いました。」


[作業場の近くの山も整備中] [次世代へつなぐ思いを込めて、新しい木を植えている]
◎活動のやりがい
『ゴジョる』は、互いの助け合いを創ろうというのがヴィジョンで、団体名もそこからきています。菊池さんは、地域に仕事を生み報酬を得て、自分たちで地域内の経済をまわすといった「持続可能性」のあるコミュニティこそ大事だ、と言います。理想と現実のすり合わせの連続でご苦労も多いと思われる中、活動のやりがいについてお伺いしました。
(菊池さん)「通常の仕事では自己責任で終わってしまうことも多いですよね。私たちは、個人が少しの力を出しあってお互い助け合う事業を展開しており、それを皆さんが面白いと言ってくださることがやりがいと感じています。私たちの活動のベースは福祉にあります。人口減少するまちで、なにか景気のいい話、釜石にいれば生涯生きていけるよねという空気をつくれたらいいかなと。孤立・孤独・困窮・環境といった社会問題の解決に向けて、私たちがアクションを起こすことで地域に受益者を生みだす仕組みを整えたい。そこにこの活動の面白みがあると感じています。」
|
~ みんながいきいきと働くための工夫について 作業場の取材から見えてきたこと~ 軽い冗談も飛び交う明るい作業場。作業していた人からは「周りがいい人たちだからやってるの」といった声も聞かれた。仕事は日中の数時間のみで休憩時間もしっかり確保し、日当はその日のうちに現金で支給される。薪を割る作業は機械を使うため、作業は薪のセッティングが中心で軽作業だ。また地元の社協と人材の情報は共有し、各人の状況に見合ったシフト調整も行っている。作業場で労働者がいきいきと働くため、菊池さん達が細やかな心配りをされているところを随所に感じることができた。
|
◎今後について
釜石発のソーシャルビジネスとして、多くの方に知られるまでに成長したゴジョる。 将来に向けたビジョンをどのように描いているんでしょうか。
(菊池さん)「ゴジョるは今後、釜石の他に同様のスキームで環境と福祉を中核とした事業の水平展開を考えています。まずは現在商品を物流を使用して搬出している八戸・花巻・北上・仙台近郊のエリアで、地域に根差した事業者さんに業務のやり方を教えて、販売までやってもらい地域活性化と環境保全の一助になって欲しいと考えています。釜石では林業で組み立てましたが、各地域の地域資源を生かしてやっていただけたら。ご協力いただける事業パートナーさんを、もっと増やしていきたいですね。」

[小さな山から箱崎漁港が見える]
取材の最後に、作業場のほど近くの小さな山にご案内いただきました。 雲の合間から太陽が防潮堤の上に薄陽を落とし、その右側には小型の船が海にいくつか浮かんでいます。その場所を眺めつつ、菊池さんは更なる夢を話してくれました。
(菊池さん)「薪の事業体はできたのですが、地域が自立するためには他にも事業体が欲しいと考えています。釜石の海の地域資源として知られる海藻類は、まだまだ製造と販売を増やせる可能性があるんですが、漁港でワカメをボイルするために使う重油の価格が高いんです。であれば、マイクロバイオマスを導入し近隣の里山整備で排出される木材を活用し、発電ではなく熱利用を核としてワカメをボイルできないかと考えています。それができればコストも下がるし、環境にも優しいんじゃないかと。今、市内の企業さんと色々検討しているところです。この地域内で人もお金も循環する流れを作れば、本当に持続可能なまちになります。そんな地域の未来に向かって、ワクワクしながらチャレンジを続けていきたいと思います。」
【お問い合わせ先】
(一社)ゴジョる釜石支店 info@gojoru.org
Facebook:https://www.facebook.com/gojorunews<外部リンク>
(取材担当:とうげ)
<注意> ※本文記事・写真・画像の無断転載は禁止させていただきます。