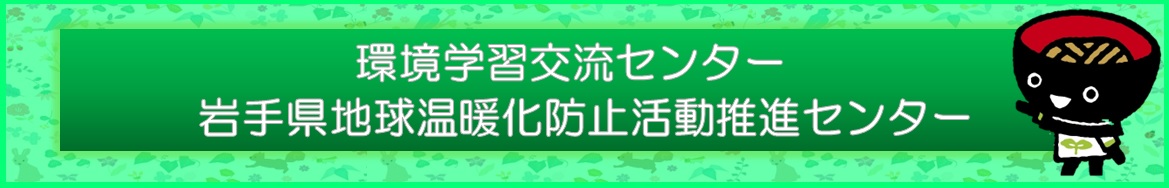2024年度 一関地球温暖化対策地域協議会 環境セミナー
「南極から見る地球の未来」
- 2024年度 一関地球温暖化対策地域協議会 環境セミナー
「南極から見る地球の未来」 参加レポート

<環境セミナー 開催概要>
■開催日時:2024年5月25日(土)15:00~17:00
■場所:一関保健センター 多目的ホール
■講師:63次隊南極観測越冬隊
岩手日報一関支社 編集記者 菊池 健生氏
<講演を伺っての感想>
2021年11月~1年4カ月63次隊南極観測越冬隊に日本新聞協会の代表記者として同行された菊池氏の貴重な体験のお話は、最初から楽しくワクワクするものでした。
南極大陸の氷の厚さはどのくらいあると思いますか。
答えは4000メートル。なんと富士山より高いのです。驚きですよね。
(この厚い氷から世界では82万年前の氷をとることに成功していて日本は現在72万年前。今後100万年前の氷を取りCO2濃度やその当時の大気の様子を調べるそうです。)
菊池氏が参加した63次隊は、コロナ感染症の関係で空港が使えず船で南極の昭和基地に向かいました。日本から14000㎞離れた基地には船でおよそ40日をかかります。
昭和基地周辺の気温は、真冬でマイナス45℃、マイナス89度になることもあるそうで、お湯が一瞬で氷になり、白い粉になるそうです。
昭和基地には、越冬隊員夏隊49名、越冬隊員32名、交代要員4名で構成されていてオーロラ・宇宙・岩石・地質・雪氷・大気の研究者、医師、コックさんがいます。皆が任務分野以外も協力していて社会の縮図のようだと感じたそうです。
南極では様々な研究が行われています。
南極の氷床を調べることによって地球の温度変化を調べています。現在日本は72万年前まで調べていて、今後100万年前の調査に入るための準備として、今回の63次隊は、調査建屋を作る作業を行いました。またこれまでの研究結果からCO2の濃度の変化と気温の変化は同期していて同じ幅で増えていることが確認できました。
コウテイペンギン、アデリーペンギン、アザラシなど極寒の地で暮らす様々な生き物がいる南極で問題となっているのがゴミです。現在日本は毎年持ち帰っているのですが、他国の基地では置きっぱなしのゴミがあり、全てのゴミを撤去するには15年かかると言われています。
菊池氏は、ゴミ問題、地球温暖化について、南極の土地や生活から地球の変化を感じてきました。
地球は大きいが人間は小さい。そして人間は簡単に自然を壊してしまう。ですが人間は力を合わせると大きなことが出来る。
日本新聞協会の代表取材で南極63次隊に参加された菊池健生氏、南極大陸の500日の記録は語りつくすことができないない出来事がたくさんあったのではないでしょうか。自然界の美しさ、動物たちとの触れ合い、ブリザードの脅威など、どれをとっても貴重な体験であると思います。
研究の根本にある過去と現在の比較でわかる大気と気温の状況はとても興味深く、CO2濃度と気温の変化が同期していることは、温暖化の原因である温室効果ガスにあることを示しているといえます。このような研究の重要性と相反する形のごみ問題も、これから解決しなければいけないことと感じた環境セミナーでした。
(記:センタースタッフ)